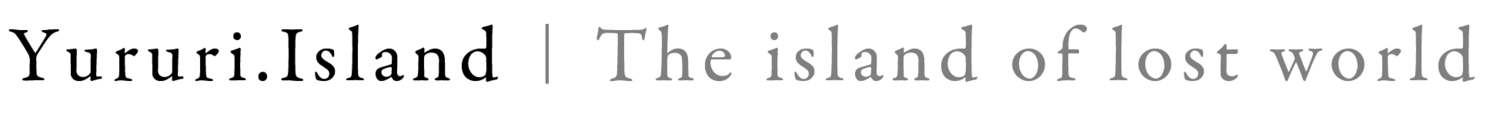Marine Animals
海獣が語る根室の海の豊かさ
|
大正時代、ユルリ島とモユルリ島では狐が飼われていたという記録があります。「北日本養狐」という会社がユルリ島には柵飼いの養狐場を設け、モユルリ島では自然放牧の形で、合わせて数十匹を飼育し、その毛皮を販売していました。ただその事業は、およそ10年程度で閉じられてしまったようです。根室半島の太平洋岸が流氷で覆われた年に、狐たちが一斉に氷を渡って逃げ去ってしまったことが、その原因だったといわれています。島々は離れているように見えても、実は海によってつながっている。そんなことをこの事件は教えてくれているのかもしれません。そう、海とは陸と陸とを隔てる存在であると同時に、それらをつなぎ、結びつける存在でもあるのでしょう。
陸生生物の狐でさえ、条件が揃えば海上を移動するのですから、ましてや普段から海に暮らす獣たちが広範囲な場所に出没するのは当然でもあるのでしょう。ユルリ島の周囲にも多くの海獣が頻繁に姿を現します。ゼニガタアザラシやゴマフアザラシ、さらに近年ではラッコを目にする機会も増えてきました。ラッコはかつて道東に生息していたものの、毛皮を取るために乱獲されて絶滅したとされていました。しかしいまではユルリ島から昆布盛の漁港にかけての水域で一度に数頭を目撃することも珍しくはなく、2014年からはユルリ島とモユルリ島で繁殖も確認されています。
こうした海獣が多く現れるのは、ユルリ島付近の海が豊かである証拠といってもいいはずです。ユルリ島に馬が運び込まれたのは昆布の漁に必要とされたためであったことはすでにご案内しましたが、現在にまで続くその昆布漁の隆盛ぶりは昆布盛という地名にも刻まれています。さらにユルリ島周囲の海を管轄する落石漁業協同組合では一年を通してさまざまな海産物を水揚げしており、とりわけサケ漁、サンマ漁、カニ漁、ウニ漁などが盛んに行われています。アザラシなどの海獣は高次捕食者とされ、海をめぐる生態系の頂点に立つ存在。そんな海獣たちが集まってくるということからも、このユルリ島周辺の海に彼らの餌となる魚介がどれほど豊富に存在しているかが知れるわけで、人間の目にはややユーモラスに映る海獣たちの姿は、実は海中の生命が形作るピラミッドの、裾野の広がりを示しているともいえるのです。そう、海獣が暮らすユルリの海は、まさに“宝の海”なのです。
ユルリ島付近の海獣については、すでに明治の初めの松浦武四郎の文章にもその記述を見出すことができます。現在は花咲線が走る根室半島の南岸を進んだ武四郎は、「ハナサキ、是和語鼻岬なるか」と花咲の語源を考察しながら「前に二島(ユルリ周二里、モユルリ周一里余)を海上二里斗に見たり」とユルリ島を見やり、そしてこの近辺がアイヌたちの「水獣の漁場」であると記しています。それほどに、ユルリ島の海を舞台にした人と海獣とのかかわりは、長く深いのです。
しかし、そこには問題もあります。それは海獣たちによる食害です。例えば、腹を上にした姿勢で波に浮かび、体の上に乗せた石で貝を叩き割って食べるラッコの姿は、その愛らしさで見る人を和ませますが、一方でラッコは実に大食漢。冷たい海中でも体温を維持するために、自身の体重の20~30%の餌を食べるといわれています。体重40㎏のラッコであれば、一日に10㎏の魚介を食べる勘定です。魚を獲るのは苦手ともいわれるラッコはウニをとりわけ好んで食しますから、ラッコが増えればウニ漁には大きな打撃となってしまいます。漁をなりわいとする人々にとっては、ラッコを単にチャーミングな生き物と片付けることは到底できません。しかし他方では、昆布を食べるウニの数が減れば昆布漁にはプラスに働くという考え方もあります。いずれにしても生態系とは極めて微妙なバランスの上に成り立っているものであって、その力学も複雑です。ユルリの海の豊かさを、そして海に生きる人々の暮らしを、これからも長く守り続けていくためには、人と海の生き物とのかかわりはどのような形であるべきなのか。それを考えるためにも、人は常に海と対話をしていく必要があるのでしょう。