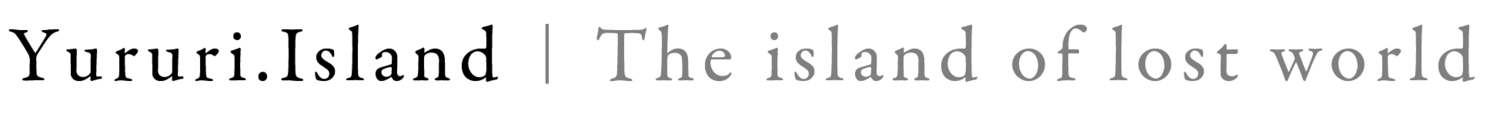Seabirds
断崖が守り育てる貴重な海鳥
|
1963年に北海道によって天然記念物に指定されて以来、北海道自然環境保全地域(1976年)、国の鳥獣保護区(1982年)、環境省選定「日本の重要湿地500」(2001年)と、さまざまな保護の対象地域に指定・選定されてきたユルリ島は、現在、上陸が制限されていて、立ち入ることができません。とりわけ入島が規制される大きな理由となっているのが、貴重な海鳥の存在です。もともと、「ユルリ」という印象的な名前は、アイヌ語で“鵜のいる島”という意味。つまりこの島はずっと以前から、海鳥の繁殖地として重要な意味を持つことが知られていたのです。いわばユルリ島のアイデンティティーともいえる海鳥は、これからも守られていく必要があります。
とりわけ、保護の対象の海鳥として重要な存在の一つに、エトピリカが挙げられます。アイヌ語で“嘴(etu)が美しい(pirka)”という意味のこの鳥は、名前の通りにオレンジ色の大きな嘴が特徴。全身は黒い羽毛に覆われていますが、顔は真っ白、そして足は嘴と同じオレンジ色と、鮮やかな色の対比が印象的な海鳥です。アメリカ、カナダからロシア、日本にかけてと分布域も広く、世界的に見れば生息数も少なくはないのですが、しかし、こと日本に限ればその個体数の激減ぶりは非常に憂慮されるところで、2019年に作成された環境省のレッドデータによれば、エトピリカは絶滅(EX)、野生絶滅(EW)に続いて状況が深刻な絶滅危惧ⅠA類(CR)に分類されています。これは「ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの」を意味していて、現在ではユルリ島とその属島であるモユルリ島(モユルリとは“小さなユルリ”の意)で数組のつがいが確認されるのみとなってしまいました。北海道大学の調査によれば、エトピリカの日本における生息数は、2015年の時点で1980年から87%も減少したと推定されています。
また、このエトピリカと並んでユルリ島を象徴する存在として、ケイマフリがいます。「Spectacled」つまり“眼鏡をかけた”という意味の英語名が表す通り、真っ黒い身体の中で目の周囲だけにレンズ状の白い模様があるチャーミングな海鳥。和名はアイヌ語の“赤い足(kemahure)”を意味していて、確かに遠くから見てもその足の鮮やかな色彩は際立っています。また“海のカナリア”とも称される美しい鳴き声も、根室半島を訪れるバードウォッチャーの間では広く知られています。前述のレッドデータでは現在のところ、エトピリカよりも絶滅の危険性が2段階低い絶滅危惧Ⅱ類(VU)に分類されていますが、とはいえ、その意味するところは「絶滅の危険が増大している種」ですから、この海鳥も決して安心できる状況にいるというわけではありません。
ユルリ島がこうした海鳥たちにとって理想的な繁殖地である理由は、その地形に鍵があります。というのも、これらの海鳥たちは実は一年の大半を陸地ではなく海上で過ごし、営巣するのは繁殖期のみ。それも外敵が寄りつかない険しい断崖に巣を作るのです。そう、外敵から卵を守るためには、峻険な断崖こそが海鳥にとって最も安らげる場所なのです。海面から急角度で立ち上がる海食崖に囲まれたユルリ島は、彼らにとって日本で最後のユートピアなのです。
鳥の正式な和名のうちでアイヌ語由来のものは、このケイマフリとエトピリカの二つだけ。それだけ、この小さな2種の海鳥は北の海辺に暮らす人々にとっては近しい存在だったのです。しかしそんな海鳥たちも生活域を狭められ、その存在を脅かされつつあります。一度の産卵でエトピリカは一つ、ケイマフリは二つしか卵を産みません。それだけに一個の卵は単なる重量以上に重い価値を持っています。その重さを想うとき、人が島への立ち入りを制限されることも、自然と納得できるのではないでしょうか。
archives
Yururi Birds
写真:有田茂生
海鳥繁殖地としての位置づけ
国指定鳥獣保護区
ユルリ・モユルリ島は、「海鳥の集団繁殖地」として、1982年に国の鳥獣保護区に指定されています。ユルリ・モユルリ島では、環境省が作成したレッドリスト(2020年)に掲載されている絶滅危惧IA類(CR)のエトピリカ、チシマウガラス、ウミガラス、ウミスズメなどの北方系海鳥類の繁殖が確認されているほか、合計で27科・47種の鳥類の生息が確認されています
北海道指定天然記念物
ユルリ・モユルリ島は、「ユルリ・モユルリ島海鳥繁殖地」として、1963年に北海道の天然記念物に指定されています。エトピリカ、ケイマフリ、チシマウガラス、ウミウ、ウトウ、オオセグロカモメ、ウミネコの海鳥類7種が繁殖し、近年減少しているエトピリカとチシマウガラスの繁殖地としては、両島が国内最後の繁殖確認地とも言われています
アカエリカイツブリ
カイツブリ目
カイツブリ科
アカエリヒレアシシギ
チドリ目
ヒレアシシギ科
アカエリヒレアシシギ
チドリ目
ヒレアシシギ科
アビ
アビ目
アビ科
アホウドリ
ミズナギドリ目
アホウドリ科
絶滅危惧Ⅱ類(VU)
アマツバメ
アマツバメ目
アマツバメ科
ウトウ
チドリ目
ウミスズメ科
ウトウ
チドリ目
ウミスズメ科
ウミウ
ペリカン目
ウ科
ウミガラス
チドリ目
ウミスズメ科
絶滅危惧IA類(CR)
ウミスズメ
チドリ目
ウミスズメ科
絶滅危惧IA類(CR)
ウミネコ
チドリ目
カモメ科
ウミバト
チドリ目
ウミスズメ科
エトピリカ
チドリ目
ウミスズメ科
絶滅危惧IA類(CR)
エトピリカ
チドリ目
ウミスズメ科
絶滅危惧IA類(CR)
エトピリカ
チドリ目
ウミスズメ科
絶滅危惧IA類(CR)
エトロフウミスズメ
チドリ目
ウミスズメ科
エトロフウミスズメ
チドリ目
ウミスズメ科
オオジシギ
チドリ目
シギ科
準絶滅危惧(NT)
オオジュリン
スズメ目
ホオジロ科
オオセグロカモメ
チドリ目
カモメ科
準絶滅危惧(NT)
オオハクチョウ
カモ目
カモ科
オオハム
アビ目
アビ科
オオワシ
タカ目
タカ科
絶滅危惧Ⅱ類(VU)
オジロワシ
タカ目
タカ科
絶滅危惧Ⅱ類(VU)
カモメ
チドリ目
カモメ科
カワラヒワ
スズメ目
アトリ科
カンムリウミスズメ
チドリ目
ウミスズメ科
絶滅危惧Ⅱ類(VU)
キョウジョシギ
チドリ目
シギ科
クロアシアホウドリ
ミズナギドリ目
アホウドリ科
クロガモ
カモ目
カモ科
ケイマフリ
チドリ目
ウミスズメ科
絶滅危惧Ⅱ類(VU)
ケイマフリ
チドリ目
ウミスズメ科
絶滅危惧Ⅱ類(VU)
コアホウドリ
ミズナギドリ目
アホウドリ科
絶滅危惧IB類(EN)
コウミスズメ
チドリ目
ウミスズメ科
コオリガモ
カモ目
カモ科
コヨシキリ
スズメ目
ウグイス科
シノリガモ
カモ目
カモ科
シマセンニュウ
スズメ目
ウグイス科
シロエリオオハム
アビ目
アビ科
シロカモメ
チドリ目
カモメ科
チシマウガラス
ペリカン目
ウ科
絶滅危惧IA類(CR)
ツノメドリ
チドリ目
ウミスズメ科
ノゴマ
スズメ目
ツグミ科
ハイイロヒレアシシギ
チドリ目
ヒレアシシギ科
ハイイロミズナギドリ
ミズナギドリ目
ミズナギドリ科
ハクセキレイ
スズメ目
セキレイ科
ハシブトウミガラス
チドリ目
ウミスズメ科
ハシボソミズナギドリ
ミズナギドリ目
ミズナギドリ科
ハシボソミズナギドリ
ミズナギドリ目
ミズナギドリ科
ハヤブサ
タカ目
ハヤブサ科
絶滅危惧Ⅱ類(VU)
ヒメウ
ペリカン目
ウ科
絶滅危惧IB類(EN)
ヒメウ
ペリカン目
ウ科
絶滅危惧IB類(EN)
ビロードキンクロ
カモ目
カモ科
フルマカモメ
ミズナギドリ目
ミズナギドリ科
ベニマシコ
スズメ目
アトリ科
ホオジロガモ
カモ目
カモ科
ミミカイツブリ
カイツブリ目
カイツブリ科
ヨシガモ
カモ目
カモ科
ワシカモメ
チドリ目
カモメ科
ワタリガラス
スズメ目
カラス科
番外編
ゼニガタアザラシ
食肉目
アザラシ科
準絶滅危惧(NT)
番外編
ゼニガタアザラシ
食肉目
アザラシ科
準絶滅危惧(NT)
番外編
ラッコ
食肉目
イタチ科
絶滅危惧IA類(CR)
番外編
ラッコ
食肉目
イタチ科
絶滅危惧IA類(CR)
番外編
カマイルカ
クジラ目
マイルカ科
番外編
マンボウ
フグ目
マンボウ科
環境省レッドリストカテゴリー
絶滅(EX)=日本ではすでに絶滅したと考えられる種
野生絶滅(EW)=飼育・栽培下あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ存続している種
絶滅危惧I類(CR+EN)=絶滅の危機に瀕している種
絶滅危惧IA類(CR)=ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの
絶滅危惧IB類(EN)=IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの
絶滅危惧Ⅱ類(VU)=絶滅の危険が増大している種
準絶滅危惧(NT)=現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種
※2020年時点での分類