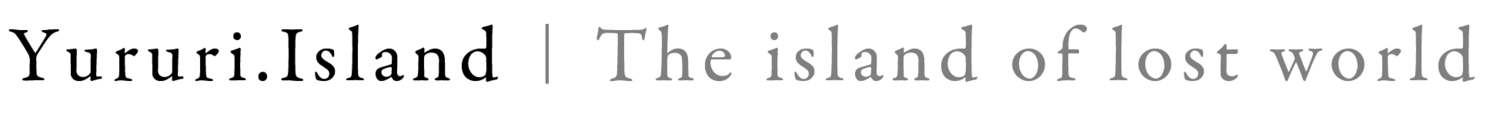Flowers
海霧の中に隠された高層湿原
|
海面上に薄い円盤を置いたような、平らで横に長い島影が印象的なユルリ島。台地の上に建てられた「緩島灯台」が放つ光も、それを遮る起伏が一切ないために周囲すべての方向にあまねく届き、沖を行く船にとって貴重な道しるべとなります。対岸の半島から見る人の目にも、とりわけ夕暮れや明け方には、この無人島の灯台のかすかな光は詩的な美しさを閃かせて映ります。そしてそんな灯台の足元近くから島の中央部一帯に広がって、この島の植生や地形・地質の特徴を決定づけているのが、なだらかな高層湿原です。
高層湿原とは植物の遺骸が泥炭となって積み重なり、それが周囲よりも盛り上がるまでになった湿原で、枯れた植物や落ち葉などを分解する微生物が活動できない寒冷な土地や高地、あるいは過湿の場所などに形成されます。周囲よりも高くなっているために水が流れ込むことがなく、それゆえ高層湿原は雨水や雪解け水だけで維持されることになるのが一般的です。ここユルリ島の高層湿原も、起伏のない平坦な土地に広がっているため、湿原目指して流れ込んでくる川などはありません。ただこの湿原の水は雨や雪に加えて、他の高層湿原とはまた違う現象によってももたらされているのです。
それが海霧です。根室半島周辺では、とりわけ春から夏の終わりにかけては、毎日のように霧が発生します。これは太平洋上の高気圧から流れ込む暖かい空気が、寒流が通過する根室沖の冷たい海水面に触れるために起こる現象で、やや古い資料になりますが昭和22年から26年までの5年間で、根室では849回の霧の発生を見たという報告もあります。年間を通じての発生確率が45%もあるとするなら、なかでも霧が生まれる条件が整う夏場には、毎日が霧といっても大げさではありません。そしてユルリ島も包み込むこの海霧が、湿原を成長させてきたのです。高地で見られることが多い高層湿原が、海抜わずか30~40mほどのユルリ島に広がっているのは、この海霧が運ぶ水によるのです。
この根室特有の海霧は、根室半島の植生にも大きな影響を及ぼしています。例えば根室半島に点在する湿原ではいくつかの“レリック(遺存種)”を見ることができます。氷河期などに広く分布していたものの、気候が温暖になるとともに高山などに取り残されるようにして根づくだけとなった植物がこう呼ばれるのですが、根室ではそれが低地にも残されているのです。ユルリ島の対岸である落石岬で花をつけるサカイツツジ(境躑躅)などはその代表といえるでしょう。それだけ根室半島一帯の生態系は独特で貴重なのです。もちろんユルリ島にもそれは当てはまります。というよりも、海霧に育まれたユルリ島の高層湿原こそ、そうした貴重な植物の宝庫と呼べるかもしれません。歴史的にも入島者が極めて少なかったユルリ島には北方系の代表的な植物のほとんどが網羅され、その種類は300種を超えるという報告もあります。さらにその中には、ヤチラン(谷地蘭)=絶滅危惧ⅠB類(EN)、ヒメツルコケモモ(姫蔓苔桃)=絶滅危惧Ⅱ類(VU)、ヒメワタスゲ(姫綿萱)、トキソウ(朱鷺草)=いずれも準絶滅危惧(NT)など、環境省レッドリストに収録されている野草も少なくありません。ユルリ島とはいわば、道東の貴重な植物を一つの場所の中に集めた、まれに見る自然の植物園でもあるのでしょう。
また、ユルリ島の高層湿原に湛えられた清らかな水が恩恵をもたらしているのは、植物だけではありません。ここに集まった水はやがて湿原を発し、ごくわずかな勾配を静かに海に向けて流れ下る幾筋かの沢を形作ります。ユルリの馬たちはこの沢の水で喉を潤し、命をつないでいるのです。隔絶された世界に生きる馬たちにとっても、この高層湿原の水は、まさに命の水なのです。海霧が作り出す奇跡的なまでの微妙なバランスの上にユルリ島はあり、そしてユルリ島の生き物たちもあるのです。ユルリ島は、だからどうしても根室沖にある必要があった。この場所でのみ起こる自然の連環の中に、彼らの生はあるのです。
今日も島は海霧の向こうに霞んでいます。まさに、幻の島。その幻の中では、誰に知られることもなく高地の花が咲き、そして馬が眠っているのです。
archives
Yururi Flowers
写真:ねむろ花しのぶ会
自然環境保全上の位置づけ
日本の重要湿地500
ユルリ島の中央部にある高層湿原は、2001年に環境省により「日本の重要湿地500」に選定されています。ユルリ島湿原には、環境省が作成したレッドリスト(2020年)に掲載されている絶滅危惧ⅠB類(EN)のヤチラン、カンチスゲなどをはじめ、絶滅危惧Ⅱ類(VU)のヒメツルコケモモ、準絶滅危惧(NT)のヒメワタスゲ、トキソウなど、絶滅が危惧されている希少な植物が数多く生育しています
道自然環境保全地域
ユルリ島は、1976年に北海道の自然環境保全地域に指定されています。道自然環境保全地域とは、国が指定する自然環境保全地域に準ずる土地の区域で、その区域の周辺の自然的社会的諸条件からみて、自然環境を保全することが特に必要な地域に対し、道が北海道自然環境等保全条例に基づき指定しています。道内ではユルリ島をはじめ7箇所が道自然環境保全地域に指定されています
5月の花
エゾイヌナズナ
アブラナ科
イヌナズナ属
エゾエンゴサク
ケシ科
キケマン属
日本固有種
エゾノクサイチゴ
バラ科
オランダイチゴ属
日本固有種
エゾネコノメソウ
ユキノシタ科
ネコノメソウ属
オオバナノエンレイソウ
シュロソウ科
エンレイソウ属
キバナノアマナ
ユリ科
キバナノアマナ属
クロマメノキ
ツツジ科
スノキ属
日本固有種
クロミノウグイスカグラ
スイカズラ科
スイカズラ属
ザゼンソウ
サトイモ科
ザゼンソウ属
シコタンキンポウゲ
キンポウゲ科
キンポウゲ属
準絶滅危惧(NT)
クリンソウ
サクラソウ科
サクラソウ属
日本固有種
チシマウスバスミレ
スミレ科
スミレ属
絶滅危惧Ⅱ類(VU)
チシマネコノメソウ
ユキノシタ科
ネコノメソウ属
トモシリソウ
アブラナ科
トモシリソウ属
絶滅危惧Ⅱ類(VU)
オノエヤナギ
ヤナギ科
ヤナギ属
ヌマハコベ
ヌマハコベ科
ヌマハコベ属
絶滅危惧Ⅱ類(VU)
ヒメイチゲ
キンポウゲ科
イチリンソウ属
ヒメシャクナゲ
ツツジ科
ヒメシャクナゲ属
ヒメシャクナゲ
ツツジ科
ヒメシャクナゲ属
フデリンドウ
リンドウ科
リンドウ属
マイヅルソウ
キジカクシ科
マイヅルソウ属
ミズバショウ
サトイモ科
ミズバショウ属
ユキワリコザクラ
サクラソウ科
サクラソウ属
日本固有種
6月の花
イワツツジ
ツツジ科
スノキ属
イワベンケイ
ベンケイソウ科
イワベンケイ属
ウツボグサ
シソ科
ウツボグサ属
エゾゴゼンタチバナ
ミズキ科
サンシュユ属
準絶滅危惧(NT)
エゾノキリンソウ
ベンケイソウ科
キリンソウ属
エンコウソウ
キンポウゲ科
リュウキンカ属
カラフトイソツツジ
ツツジ科
ツツジ属
カラフトダイコンソウ
バラ科
ダイコンソウ属
キジムシロ
バラ科
キジムシロ属
キヨシソウ
ユキノシタ科
ユキノシタ属
絶滅危惧IA類(CR)
クロユリ
ユリ科
バイモ属
コケモモ
ツツジ科
スノキ属
シコタンタンポポ
キク科
タンポポ属
日本固有種
シロツメクサ
マメ科
シャジクソウ属
シロバナハクサンチドリ
ラン科
ハクサンチドリ属
スズラン
キジカクシ科
スズラン属
セイヨウタンポポ
キク科
タンポポ属
センダイハギ
マメ科
センダイハギ属
タカネナナカマド
バラ科
ナナカマド属
チシマキンバイ
バラ科
キジムシロ属
チシマフウロ
フウロソウ科
フウロソウ属
ツマトリソウ
サクラソウ科
オカトラノオ属
ツルコケモモ
ツツジ科
スノキ属
ネムロシオガマ
ハマウツボ科
シオガマギク属
絶滅危惧Ⅱ類(VU)
ハクサンチドリ
ラン科
ハクサンチドリ属
ハマナス
バラ科
バラ属
ハマハコベ
ナデシコ科
ハマハコベ属
ハマボウフウ
セリ科
ハマボウフウ属
ヒメイズイ
キジカクシ科
アマドコロ属
ヒメツルコケモモ
ツツジ科
スノキ属
絶滅危惧Ⅱ類(VU)
ミツバオウレン
キンポウゲ科
オウレン属
ワタスゲ
カヤツリグサ科
ワタスゲ属
7月の花
エゾノシモツケソウ
バラ科
シモツケソウ属
オオカサモチ
セリ科
オオカサモチ属
オオハナウド
セリ科
ハナウド属
オトギリソウ
オトギリソウ科
オトギリソウ属
ギョウジャニンニク
ヒガンバナ科
ネギ属
クルマユリ
ユリ科
ユリ属
シロバナニガナ
キク科
ニガナ属
テガタチドリ
ラン科
テガタチドリ属
トキソウ
ラン科
トキソウ属
準絶滅危惧(NT)
ノビネチドリ
ラン科
ノビネチドリ属
ノリウツギ
アジサイ科
アジサイ属
バイケイソウ
シュロソウ科
シュロソウ属
ヒオウギアヤメ
アヤメ科
アヤメ属
ヒメワタスゲ
カヤツリグサ科
ヒメワタスゲ属
準絶滅危惧(NT)
フタマタイチゲ
キンポウゲ科
イチリンソウ属
絶滅危惧Ⅱ類(VU)
マルバトウキ
セリ科
マルバトウキ属
モウセンゴケ
モウセンゴケ科
モウセンゴケ属
ヤマブキショウマ
バラ科
ヤマブキショウマ属
8月と9月の花
イヌタデ
タデ科
イヌタデ属
イワツツジ
ツツジ科
スノキ属
ウメバチソウ
ニシキギ科
ウメバチソウ属
エゾイヌゴマ
シソ科
イヌゴマ属
エゾオグルマ
キク科
ノボロギク属
エゾカワラナデシコ
ナデシコ科
ナデシコ属
エゾゴゼンタチバナ
ミズキ科
サンシュユ属
準絶滅危惧(NT)
エゾノシシウド
セリ科
エゾノシシウド属
エゾノレンリソウ
マメ科
レンリソウ属
エゾフウロ
フウロソウ科
フウロソウ属
エゾミソハギ
ミソハギ科
ミソハギ属
エゾヤマハギ
マメ科
ハギ属
エゾリンドウ
リンドウ科
リンドウ属
オオバコ
オオバコ科
オオバコ属
オニシモツケ
バラ科
シモツケソウ属
オミナエシ
スイカズラ科
オミナエシ属
カラフトアザミ
キク科
トウヒレン属
絶滅危惧Ⅱ類(VU)
カラフトノダイオウ
タデ科
ギシギシ属
絶滅危惧Ⅱ類(VU)
カラフトブシ
キンポウゲ科
トリカブト属
キタノコギリソウ
キク科
ノコギリソウ属
絶滅危惧Ⅱ類(VU)
キンミズヒキ
バラ科
キンミズヒキ属
クサフジ
マメ科
ソラマメ属
クサレダマ
サクラソウ科
オカトラノオ属
コケモモ
ツツジ科
スノキ属
コハマギク
キク科
キク属
日本固有種
サラシナショウマ
キンポウゲ科
サラシナショウマ属
サワギキョウ
キキョウ科
ミゾカクシ属
シカギク
キク科
シカギク属
シロバナエゾフウロ
フウロソウ科
フウロソウ属
シロバナタチギボウシ
キジカクシ科
ギボウシ属
シロバナツリガネニンジン
キキョウ科
ツリガネニンジン属
タカネナナカマド
バラ科
ナナカマド属
タチギボウシ
キジカクシ科
ギボウシ属
タマミクリ
ガマ科
ミクリ属
準絶滅危惧(NT)
チシマコハマギク
キク科
キク属
絶滅危惧Ⅱ類(VU)
ツリガネニンジン
キキョウ科
ツリガネニンジン属
ツルコケモモ
ツツジ科
スノキ属
トウゲブキ
キク科
メタカラコウ属
ナガボノシロワレモコウ
バラ科
ワレモコウ属
ナミキソウ
シソ科
タツナミソウ属
ネジバナ
ラン科
ネジバナ属
ハチジョウナ
キク科
ノゲシ属
ハナイカリ
リンドウ科
ハナイカリ属
ハマエンドウ
マメ科
レンリソウ属
フランスギク
キク科
フランスギク属
ホソバノキソチドリ
ラン科
ツレサギソウ属
ミゾソバ
タデ科
イヌタデ属
ミミコウモリ
キク科
コウモリソウ属
ミヤマアキノキリンソウ
キク科
アキノキリンソウ属
ムラサキツメクサ
マメ科
シャジクソウ属
ヤチラン
ラン科
ヤチラン属
絶滅危惧IB類(EN)
ヤナギタンポポ
キク科
ヤナギタンポポ属
ヤマハハコ
キク科
ヤマハハコ属
環境省レッドリストカテゴリー
絶滅(EX)=日本ではすでに絶滅したと考えられる種
野生絶滅(EW)=飼育・栽培下あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ存続している種
絶滅危惧I類(CR+EN)=絶滅の危機に瀕している種
絶滅危惧IA類(CR)=ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの
絶滅危惧IB類(EN)=IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの
絶滅危惧Ⅱ類(VU)=絶滅の危険が増大している種
準絶滅危惧(NT)=現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種
※2020年時点での分類