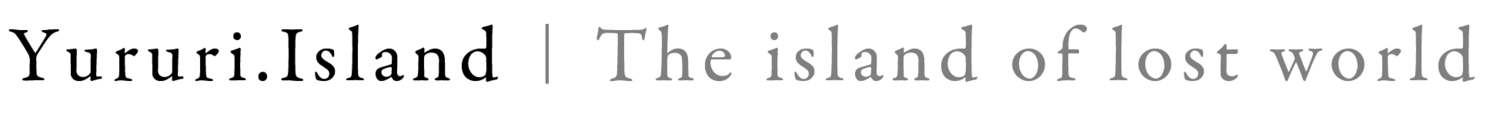Flowers
花園効果と白い花弁の不思議
|
ユルリ島が楽園である理由。もちろんまずそれは、人間の営みが途絶えたまったくの無人の世界の中で、野生化した馬たちだけが、ある時は霧の立ち込める草原に立ち尽くし、またある時は朝陽に光り輝く雪原を駆け巡るという、ほかのどんな場所でも見ることのない詩的な情景がこの島では繰り広げられているという点に求められます。しかしそれとともに島の表面を覆い尽くした草花が織り上げる風景もまた、ここが楽園と呼ばれるにふさわしい場所であることを証明しているといえるでしょう。断崖に囲まれた島の、その崖を登りきった瞬間に眼前に広がる風景。それと似たものを探そうとするなら、地上のほかの場所よりも、いつかの夢で見た風景を思い浮かべたほうが早いかもしれない。そんなことまで思わせるほどに、ユルリ島の風景は繊細で、そして独特です。
そんな夢の中のような風景が形作られるうえで大きな影響があったと考えられているのが、“花園効果”です。これは草原に馬を放牧した際などに起こると考えられている現象で、草丈の高いイネ科やカヤツリグサ科の植物が、それらを馬が好んで食べるために食圧によって丈を抑えられてしまい、本来ならそれらの陰になって勢力を維持することが難しいはずのフウロソウ科やユリ科、キキョウ科、アヤメ科、ラン科などの丈の低い植物がより旺盛に繁茂できるようになることを指します。そうしてより広い領域を占めることになった植物群は、その多くが小さな花をつける野草なのです。そのためユルリ島は花の季節を迎えると、島全体が可憐な花の色が織り込まれた、見渡す限りの緑の絨毯と化すのです。
現在、ユルリ島で暮らしている馬たちのルーツは、終戦後に島に昆布番屋を建てた漁師たちが連れて渡った馬ですが、しかしこの島ではおよそ100年前の大正時代にはすでに馬たちが自然放牧をされていたという記録があり、それだけの長い期間にわたる馬とのかかわりの中で、こうした花園効果が進んだものと考えられます。断崖の上の台地に広がるユルリ島の草原では、夏に咲くタチギボウシ(立擬宝珠)や晩夏から秋にかけて花をつけるナガボノシロワレモコウ(長穂の白吾亦紅)の群落が形成されています。地面を覆い尽くした柔らかな緑の草原に、それらの花々が咲き揃う稀有な情景。この島で生き続けてきた馬たちがもたらした、それはまさしく自然の花畑、洋上に浮かぶ奇跡の花園なのです。
そしてそんな人知れず広がるユルリ島の花畑には、大きな不思議も隠されています。というのも、本来であれば爽やかな色を帯びた花弁をつけるはずのいくつかの植物が、ここではなぜか白い花を咲かせるのです。前述のユリ科のタチギボウシやラン科のハクサンチドリ(白山千鳥)、フウロソウ科のエゾフウロ(蝦夷風露)、さらにキキョウ科のツリガネニンジン(釣鐘人参)やシソ科のウツボグサ(靫草)、マメ科のクサフジ(草藤)など、いずれも紫がかった花をつけるのが特徴の植物たちですが、そうした本来の色に加えて白い色で開花した個体をユルリ島の草原の中では数多く発見することができるのです。
これらはそれぞれ“シロバナタチギボウシ”や“シロバナハクサンチドリ”などと呼称されますが、どうしてユルリ島にこれほど多様な白花品種が根づいているのかは解明されていません。いずれもそれらが紫の虫媒花であることからすると、白い花を咲かせることで効果的に虫を引き寄せる特有の条件が根室半島周辺にあったとも考えられますし、それがユルリ島でとりわけ多く見出されるのは、長く無人島であるために盗掘を免れたからではないかという指摘もされますが、現在ではまだそうした可能性が論じられている段階です。つまりユルリ島に咲く白い花はいわば、この島だけに秘められた美しい謎の一つなのです。そして、あるいは謎のままでもあってもいいのかもしれません。もしかしたら楽園とは、いくつもの謎や秘密が組み合わさって初めて、その姿を現すものなのかもしれないのですから。