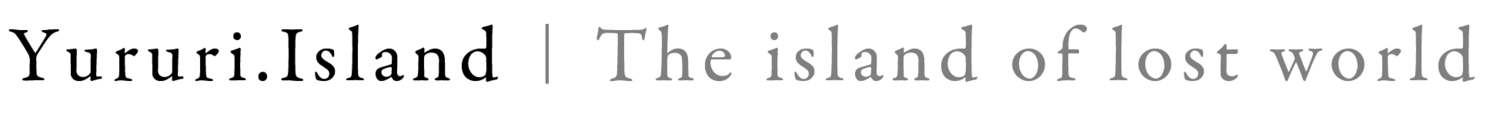Horses
理想郷を支えた名牧場の記憶
|
ゆるやかにうねりながら続く草原を海からの風が吹き抜けていき、その通り道の道筋を静かに揺れる可憐な野草が教えてくれる……。花咲線の別当賀駅から海に向かう一帯では、訪れる人はそんな美しい詩情を湛えた絵画のような風景と出会うことができます。このフレシマ湿原と呼ばれる場所にはかつて、壮大な牧場が広がっていました。道東の馬産の黎明期に根室畜産組合を組織し、その隆盛を導いた佐藤藤作氏が開いた佐藤牧場です。吹き寄せる強い潮風が馬の餌となる緑の草に塩分をもたらし、さらに冬季にはその草の上に積もった雪を吹き飛ばすために、フレシマは北辺にあっても年間を通して馬を育てることができる、それは優れた放牧地であったのです。最盛期にはおよそ120頭にも達する雌馬と2~3頭の種馬が、この美しい草原に放たれていたといいます。
そしてこの佐藤牧場、一名フレシマ牧場は、ユルリ島とも深いつながりを持っていました。というのも、ユルリ島に馬を供給する役割をこの牧場が担っていたからです。ユルリ島では住人であった庄林庄治氏が、収穫した昆布を崖の上に設けられた干場まで引き上げるために昭和26~27年頃に雌馬一頭を島に運び込んでいて、これが現在に続くユルリ島の馬の最初の一頭とされていますが、続いて昭和33年ごろに住人に貸すための馬を佐藤家が持ち込んだのだそうです。また、そのおよそ10年後には種馬となる雄馬が佐藤牧場から連れてこられた記録も残されています。元来、無人島であったユルリ島に人が住んでいた期間はさして長いものではなく、昭和46年には最後の一軒となった庄林家が島を後にし、そうして馬だけが島に残されることになったわけですが、その馬たちを守り育んだのは、佐藤牧場だったのです。
住人が去った後のユルリ島には自然放牧場としての魅力的な要素が実はいくつも備わっていました。馬の食餌となるアイヌミヤコザサが島の地面を覆うように繁茂していて、馬に飼料を与える必要がありません。潮風がその笹に塩分を運ぶことや、その上に雪を降り積もらせない役割を果たすことは対岸のフレシマ湿原と同様ですが、それに加えて島はもとより周囲の土地と隔てられているため、馬が逃げ出さないように柵で囲う作業も見張る手間もかかりません。ただ近親交配を避けるために定期的に種馬を入れ替える必要があり、また牧場の経営という観点から島で新たに生まれた馬のうちの雄の一歳馬はセリにかけるために島から連れ出す必要もありました。こうした、いわば馬の理想郷としての環境を守るための作業には、佐藤藤作氏らの熟練の技が大きな貢献をしていました。
根室の馬産のパイオニアである佐藤牧場は、戦前には国後島や色丹島にも馬を買い付けに赴いたことがあったといいます。これらの島で日本釧路種や奏上釧路種に近い、道東ならではの馬が大量に生産されていたためですが、この際に採られた、陸地を駆ける馬を投げ縄によって捕らえ、馬の鼻に水が入らないように小舟を使って曳き泳がせ、沖で大型の船に積み込んで海を渡るという手順は、佐藤牧場の豊富な経験から編み出された独特のものでした。そしてこうした方法を応用することで初めて、ユルリ島の馬を出し入れすることも可能になったのです。
馬種の改良をライフワークとした佐藤藤作氏は、自らの理想とする馬を「四肢のしっかりした、比較的小型の、目のぱっちりした馬」と表現していたといいます。「目のぱっちりした」という言葉は少々意外なものに響きますが、氏はそれを「素直な頭の良い馬」といった意味で使っていたそうです。素直さ、頭の良さは目に現れるということなのでしょう。そしてユルリ島に最も長く暮らした庄林庄治氏の子息である庄林泰三氏(2021年に逝去)は生前、島に生きていた馬について、こう追想していました……。「人が間違ったことをしさえしなければ、馬はいつだって優しくて従順で、頼りになったんだ」と。
それは佐藤藤作氏が理想として掲げた馬のありように他なりません。つまり佐藤牧場は、まさに理想の馬を生み出すユートピアだったのです。その証となる馬が、ユルリ島には確かに生きていたのです。そしてその末裔たる馬たちがいま、ユルリ島に残されているのです。
archives
Yururi 19XX
写真:佐藤正一郎
ユルリ島で受け継がれていた島での馬追いと船による馬の運搬の様子。撮影年不詳