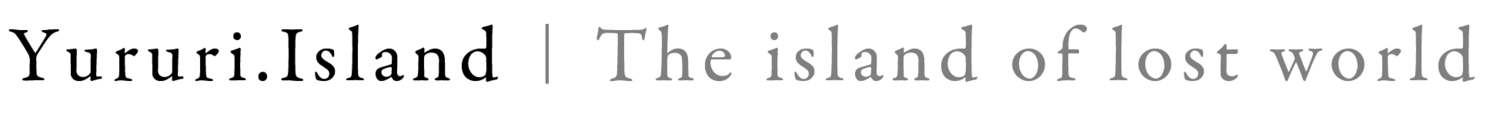Horses
道東の馬に息づく気高い血脈
|
広大な北海道の大地を走る鉄道路線の中で、(支線部を含めない幹線路線としては)最長となる鉄道路線がJR根室本線ですが、日本の最東端を走る総延長およそ444㎞に及ぶこの鉄路の中でも、とりわけ釧路と根室とを結ぶ区間には“花咲線”の愛称がつけられ、その車窓に映る風景の美しさで広く愛されています。そしてこの花咲線が走る一帯は、実は日本の馬産の歴史における聖地ともいうべき土地でした。
近代日本の馬産、つまり馬の生産や飼育の成り立ちをひもといていくと、その中心地となっていたのが根室と釧路という、まさに花咲線が結んでいる二つの町であったことがわかります。日清、日露の二つの戦争を通じて在来の馬種が軍馬に適さないことが明らかとなった日本では、20世紀初頭、政府が馬政局という組織を新設。国産馬の体躯の改良に乗り出します。そして国が主導したこの取り組みにいち早く呼応したのが、根室や釧路の牧場主たちでした。彼らは独自にペルシュロン、ブルトン、アングロノルマンといった西洋種の雄馬を輸入し、“道産子”の愛称で親しまれた北海道和種と交配させることで理想の馬づくりを始めたのです。四肢が頑健で牽引力が強く、それでいて西洋種に比べれば大きすぎないために背にも荷を載せられて扱いやすい。試行錯誤を経てそんな馬を数多く生み出すに至った道東は、先進的な馬産地として名を馳せることになりました。いまも花咲線に駅名として残る根室市の厚床や同じく釧路本線にある釧路市の大楽毛に立った馬市には、人と馬とが雲霞のごとくに集まったといいます。厚床にはいまも馬頭観音を祀る碑が残されていますが、その存在感は東洋一の規模と謳われた厚床の馬市の隆盛ぶりを物語っているようです。そしてそんな記録や記憶とともに、この道東から扉が開かれた近代馬産の歴史を現代に語り伝えているのが、ユルリ島に暮らす馬たちといえるのかもしれません。
理想の馬をつくる……道東の牧場主たちのそんな情熱から生み出された馬種に“日本釧路種”があります。現在は大楽毛駅前にその体格や体型を再現した像が設置されていますが、釧路畜産組合が馬種の改良に取り組んでから約40年をかけて昭和7年に発表したこの輓馬(橇などを牽く馬)は、軍馬としてだけではなく北海道の大地を開拓するための農耕馬としても極めて優れた力を発揮しました。またその名声の高まりを受けて、昭和天皇の北海道行幸に際しては乗馬にも適した改良種として“奏上釧路種”が世に出ます。いずれも世界的な注目を集め、日本の馬産の歴史を画した名馬でした。そんな日本釧路種、奏上釧路種の血を引き継いでいるのが、ユルリ島に暮らす馬たちなのです。
戦後、農業機械が広く普及していくのに合わせて、馬は農耕において力を発揮する場を失い、その数を減らしていきます。日本釧路種も奏上釧路種もすでに姿を消しました。いや、それ以前に、道産子の祖先である東北の南部駒(南部馬)もすでに絶滅しています。しかしユルリ島の馬たちは、その馬たちだけは、そうした歴史の中に消えていった馬の在りし日の姿を現代に伝えているのです。もはや日本釧路種や奏上釧路種の末裔は、この島でしか見ることができません。
ラスコー洞窟の壁画に馬の姿が見られることからもわかる通り、馬は最も古くから人とともにあった動物の一つです。農耕に荷役にと、人は馬の力を借りながら文化を発展させてきたといってもいいでしょう。もちろん、北海道でも事情は同じで、とりわけ明治初期の入植から戦後の混乱期までの厳しい時代を、人と馬とは寄り添いながら生き抜いてきました。とりわけ、ここ道東においては、その結びつきはより強く濃いものがあったのです。花咲線、昆布盛駅から徒歩20分の昆布盛漁港の眼前に浮かぶ小さな島、ユルリ。そこでは人と馬とのかかわりの記憶をその体躯に宿した馬たちが、今日も無人の草原を自由に疾駆しているのです。
archives
Yururi 1977-1979
写真:北海道根室高等学校地理研究部
顧問の山田豊治教諭の指導のもと、1977~1979年に学生が行なったユルリ島の調査記録
日本釧路種や奏上釧路種の血を引き継ぐユルリ島の馬と昆布番屋跡など